2月22日、大阪市内で第10回私立公立高等学校IT活用セミナーを開催。稲垣俊介准教授・山梨大学教育学部は初めて実施された大学入学共通テスト「情報Ⅰ」の問題傾向と分析、近畿大学附属高等学校と兵庫県立御影高等学校は1人1台端末を活用した授業改善、大阪府立摂津高等学校と雲雀丘学園中学校・高等学校は「情報Ⅰ」におけるプログラミング実践と「データの活用」の評価方法について報告した。なお、所属等は2025年2月時点。
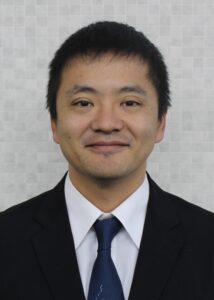
大阪府立摂津高等学校 長瀬勇輝教諭
大阪府立摂津高等学校は2024年度DXハイスクールに採択。長瀬教諭がプログラミング教育実践について報告した。
◆・◇・◆
プログラミングの授業で主に利用しているのはDXハイスクール事業で購入したmicro:bit(マイクロビット)とGoogle Colaboratory(コラボラトリー)だ。
当初は生徒たちでプログラムを作る学習を行っていたが基本的な知識・技能が定着しにくかったため、基礎を押さえた後シミュレーションで身近なテーマに落とし込む授業設計に2024年度より修正した。
順次・分岐・反復、変数の授業は、概念を学びブロックで簡単なプログラムが作成できるようになることを目標とした。マイクロビットを活用し、ハートが点滅するプログラム、カウントダウンタイマー、サイコロプログラムをブロックプログラミングで作成。最後はPythonコードに書き換え、Googleクラスルームに提出。実機を動かす実習に生徒は「すごい」と喜びながら取り組んでいた。
配列の授業では、コラボラトリーで実際にコードを入力しながら、反復処理を行うことで効率的に処理するプログラムが作成できることを体験し、変数や反復処理の意義を深めた。
関数の授業では教科の単位認定の可否を判定するプログラムを作成。同じ処理を繰り返している箇所を探し、関数にまとめ、あえて引数を渡す前に実行し、関数は呼び出さないと動かないことを経験させた。より身近なテーマとして「1円を入れても150円のジュースが買えてしまう」自動販売機のプログラムの修正にも取り組んだ。お金が足りない時に商品を売らないようにする、お釣りを計算して表示させる、不足額を計算して表示させるという3つの課題を提示した。
シミュレーションの授業では、サイコロ、ガチャ、宝くじの3つのシミュレータを使った検証を行った。事前と事後にGoogleフォームで「宝くじを大量に購入したら当たると思うか」のアンケートを実施。事後には「いいえ」の回答が増加。シミュレーションが意思決定に変化を与えたことを体験的に理解した後、実社会でも同様の技術が使われていることを押さえた。
毎授業後にアンケートを行い授業改善に活かしている。マイクロビットを使った授業後が「知識が身についた」と感じている生徒が最も多く、今後は実機を使った教材をさらに作成したい。自分ごととなるような題材をどう提供していくかが課題である。
DXハイスクールに採択されたことを受け、第2LAN教室を再整備。リース契約が終了したPCと固定式の机を撤去し、可動式の机、大型モニターを設置。ドローン、Raspberry Piも導入した。授業だけでなく、部活動の試合のふり返りなどにも活用もされている。これらの環境を使い、ブロックプログラミングで楽しく学びつつ、コーディングの良さを実感してもらい、身近な問題解決につながるようなプログラムを探究する活動に取り組みたいと考えている。
教育家庭新聞 教育マルチメディア 2025年4月21日号