2月22日、大阪市内で第10回私立公立高等学校IT活用セミナーを開催。稲垣俊介准教授・山梨大学教育学部は初めて実施された大学入学共通テスト「情報Ⅰ」の問題傾向と分析、近畿大学附属高等学校と兵庫県立御影高等学校は1人1台端末を活用した授業改善、大阪府立摂津高等学校と雲雀丘学園中学校・高等学校は「情報Ⅰ」におけるプログラミング実践と「データの活用」の評価方法について報告した。なお、所属等は2025年2月時点。
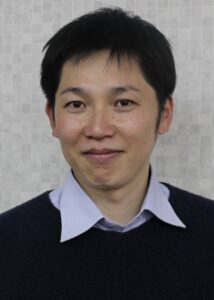
雲雀丘学園中学校・高等学校 林宏樹教諭
雲雀丘学園中学校・高等学校の林教諭はデータサイエンスを軸にした独自の探究カリキュラムと情報Ⅰ「データの活用」の授業実践を報告した。
◆・◇・◆
本校は2024年度にDXハイスクールと、文系生徒の探究活動の充実を支援するHYOGOグローバルリーダー育成事業に採択。データサイエンスがすべての探究の土台になると考え、データサイエンスを軸にした探究のカリキュラム開発に全校で取り組んでいる。
1年次はデータを活用した課題を発見する探究養成期として、総合的な探究の時間で「データサイエンス探究基礎」を全員が履修。統計的な問いの立て方を学ぶ。同時に情報Ⅰで相関分析やデータの加工について学び、客観的データに基づく考察力の育成を図る。
2年次は探究実践期で文理に分かれ特定分野に特化して課題解決を目指す。文系生徒は「データサイエンス探究実践」として地域科学実践(社会科)、スポーツ科学実践(保健体育科)、生活科学実践(家庭科・芸術科)から選択。他教科と連携し課題解決を行う。
理系生徒は情報Ⅱ、理数探究を必修とした。全員に探究させるため、DXハイスクール事業により「全国教員指導力向上研修会」をオンラインで6回実施。情報Ⅱの学習内容が実社会でどのように実装されているか、各分野の専門家による研修を行った。研修会の動画はJDSSP高等学校データサイエンス教育研究会のHPに掲載。研修会の内容をもとに教員用教材の制作も進めている。
2024年度は「フロンティアウィーク」として全教員がAIを活用した授業、大学や企業と連携した授業、教科の枠を超えた授業のいずれかに取り組んだ。AI活用は全教科で実現。実践のフィードバックを基に今後の活用についても議論を進めている。
情報Ⅰの学習内容は高度化したが、専門性を持つ情報科教員は十分に配置されておらず、特にプログラミングとデータの活用の指導に不安を抱えている。また他の教員と評価基準を比較・検討することができないことも課題となっている。
そこで、どの学校でも活用できる「データの活用」の評価基準の作成を目指して次のような研究を行った。
授業目標は相関を用いた分析ができること、データの関係を適切に考察できることと設定。成果物は評価を統一しやすいようパワーポイントのスライド1枚とした。記入する内容と生徒への指示は結果と考察の違いといった言葉の定義まで複数人で検討。指示がより明確になり、生徒が意識して結果と考察を区別するようになるなど内容の深まりにつながった。
観点別評価の指標も複数人で検討。先行研究の成果物を基に情報科教員6人が各自評価を行い、類似する項目ごとにまとめ、ソフトウェア技能力・分析力・思考的活動力の3つの観点と観点ごとの基準を設定。異なる学力レベルの学校に在籍する教員が共通認識を図りながら検討したことで生徒の実態に応じて活用できる基準となった。
授業計画は複数校が同じ内容を実施できることを前提に作成。50分×4回として相関分析の事例動画を全員で視聴した後、各自動画を見ながら散布図の作成(ソフトウェア技能力)、相関係数を求めて相関を判断(分析力)、考察(思考的活動力)という探究活動に取り組む。教員は作業のファシリテートのみ行うこととした。
動画は経産省「未来の教室」STEAMライブラリー「世界はデータで出来ている」を利用。4回では生徒の理解が不十分だった実践校はその後の授業でフォロー。初めから教員が教えるのではなく、生徒自身が悩みながら探究する活動を経たことで理解が深まったようだ。
実践には県内の高校10校が参加。1959作品の成果物が集まった。このうち実践校ごとに無作為に抽出した490作品の評価を行い、思考的活動力の到達度を軸に16段階の総合評価表を作成。どの段階の生徒が多いのかによって、焦点を当てて指導すべき力が分かるものだ。
教育家庭新聞 教育マルチメディア 2025年4月21日号