小中高等学校において「主体的・対話的で深い学び」を実現すること、そのために協調学習を引き起こす授業づくりに取り組んでいる「新しい学びプロジェクト」研究協議会と一社・教育環境デザイン研究所CoREFプロジェクト推進室は1月26日、「新しい学びプロジェクト2024年度報告会~学びをつなげる・学びでつながる~」を聖心女子大学宮代ホール及びオンラインで開催した。同協議会は2010年、加盟6団体から始まり、現在20都道府県30団体が加盟している。
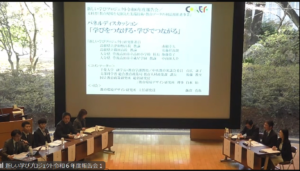
「学びをつなげる・学びでつながる」をテーマに、プロジェクト研究推進員である島根県教育委員会及び豊後高田市教育委員会の教職員が討議
本プロジェクトは、人は如何に学ぶかという学習科学の知見に基づいた取組。学習科学は1980年代に成立した学問分野である。
人が理解を深めるときは思考と対話が重要な役割を果たしている。1人ひとりの子供の学ぶ力を信じ、思考と対話による深い理解のプロセスを学習場面で引き起こす学びが「協調学習」であり、その型として考えられたものが「知識構成型ジグソー法」。新しい学びプロジェクトでは、主体的・対話的で深い学び(主・対・深)のために教員も学び合える場をつくりたいと考えている。
具体的な手立ては2つ。まず、協調学習を引き起こしやすい知識構成型ジグソー法(以下、ジグソー法)という型を利用すること。ジグソー法により1人では十分な答えが出ない課題にそれぞれが違う視点から学び、対話して組み合わせたり比べたりしてよりよい考えを活かし、そのうえで他の班の考えを聞くことでさらに理解を深め、最後に再度、個人で自分の学びの変容を整理・ふり返る。こうした型があることで、授業デザインそのものが変わるとともに、見た目の活発さから頭の中や心をどんなふうに働かせたのかに注目できるようになる。
2つめは、仮説検証型の授業研究だ。子供たちの記述や対話をもとに頭の中で起こっていることを見取ること、見取りをもとにデザインとその裏にある学びの仮説を見直し、次の授業デザインに活かしていきたいと考えている。教員は協調学習の型を学ぶことで、子供のこんな姿が見られるのではないかなど学習科学に基づいた授業研究になることがわかってきた。授業研究は授業をよりよいものにするだけではなく人の学びや人のつながりを生み出している。
この2つの取組の質を高めるために、ICT活用に力を入れている。過去の実践例のデータベース「学譜システム」は過去事例を基に授業デザインについて教員の対話を引き起こすことに役立っている。グループワークの発話や映像を記録する「学瞰レコーダ」も開発。子供のつぶやきを高い精度で記録することで、思考が変わる瞬間を捉えることができる。
学瞰レコーダとは、1人1台のピンマイクで収集した音声と360度カメラの映像を自動同期し、つぶやきまで記録できるシステム。
安芸太田町(小学校2校・中学校2校・広島県)では、教育委員会に1台、各校2台、計9台の学瞰レコーダを整備。授業研究等がある際には1校に集めて利用することもある。その際には同町のICT支援員が設置やテキスト書き起こしの事前準備などをサポート。事前に指導案と資料から発言されそうな単語を学瞰マネージャに登録することで、書き起こしの性能改善を図っている。同町のICT支援員によると年間20回以上は行っている。Wi-Fi環境も利用できるので体育館での授業にも利用しているという。
このほか飯塚市や吹田市でも同様に市が導入しておりいずれも公開授業や研究授業での利用が多い。日常使いができるように常設されることが望ましいという声も多いようだ。
安芸太田中学校の山本康美教諭は、すべての教科で協調学習を取り入れている。1年の授業参観で協調学習による「竹取物語」を公開したところ、保護者も生徒とともに考え、対話する様子がみられたという。協調学習の保護者理解に有効であったと話した。
「学びをつなげる・学びでつながる」をテーマに、プロジェクト研究推進員である島根県教育委員会及び豊後高田市教育委員会の教職員が討議した。
本校は文部科学省「新時代に対応した高等学校改革推進事業(普通科改革支援事業)」に採択されており、協調学習とICT活用を通した授業改善を柱の一つとして取り組んでいる。現在、3年間を見据えた生徒の学びのルーブリック作成を検討中だ。
2016年、既に協調学習を進めている埼玉県内の高校を視察した。ある進学校で生徒たちは、指示がなくてもどんどん学びを深めていた。様々なタイプがいる生徒の学校も、授業が始まると一気に集中して取り組んでおり、感銘を受けた。
本県でも協調学習に取り組むこととなり、協調学習マイスター(協調学習を進めるスキルをもつ教員)をチュータとしたグループで「主・対・深」を目指している。マイスターと研究推進委員を中心に、ICTを利用して県内教員が知り合う機会にもなっている。
本県は小規模校が多いためそれぞれの教科について校内で深めることは難しいが、ジグソー法という型を通じて他教科同士の教員が助言し合い連携することができる。校内では教員を生徒役にして授業案の事前検討を行っている。生徒の学びに基づいた仮説検証を行うので、改善点も見つけやすい。
初任として着任した太田高校で学習科学に出会い、ジグソー法に取り組んで6年目。生徒同士が対話を通じて、自ら考えて学ぶためにどう支援するかという視点で授業づくりを行っている。
本校は2年で進学コースと総合コースに分かれる。進学コースではスムーズに進むが同一授業案だと総合コースではつまずく場合もあり、一部を講義型にする、ワークシートの内容を変えるなど生徒の実態に応じた授業づくりを意識するようになった。
2024年度は2学期のほとんどの授業でジグソー法を用いている。生徒は情報端末を使うなどして自分で調べるようになり、対話を重ねる力がついて自分の考えに責任をもつようになり、クロストークの時間が長くなった。
生徒アンケートによると、意義があると感じる学習活動のトップが「グループで意見を共有し、議論すること」と圧倒的であった。毎時間取り組みたい、考えを伝え合うことで理解が深まった、という声もある。ジグソー法は生徒の学びを支えていると感じている。
本校は県内初の施設一体型小中一貫校。協調学習は2016年度から全学年でスタートし、当時の1年生が現在の9年生。今年度は課題解決に向けて主体的に取り組み自分の考えを伝えることができる児童生徒の育成に取り組んだ。
年度当初にジグソー法の理論研修と、過去の教材を用いた体験研修を実施。第1回校内研究会(7月)では英語と保健体育を公開するとともに学瞰レコーダを利用して対話データを取得。夏休みの教員研修で、学瞰レコーダで取得した対話の記録を基にシステムの使い方や効果については学んだ。
話の流れが変わったところがわかり、生徒の思考の変遷を見取ることができた。本システムではキーワード枠に入力すると、その言葉が対話で何回使われたかもわかる。
模擬授業でも学瞰レコーダを利用して対話を記録。授業改善に向けて有効な協議ができている。
主・対・深という言葉は浸透してきたが、理解はまちまちで、実現に向けた授業改善が必要であると感じている。一時間の授業を進めることが精いっぱいの初任教員もいる。また、経験年数を経た教員は自分のやり方が確立しており、変革しにくい面がある。
そこで8月、学譜システムの授業実践を基に、授業案を学年部全体で検討する研修を行った。すると3学期に協調学習に取り組む教員が増え、教員同士の授業改善に関する話し合いが活発になり、仮説検証型の授業研究になっていった。
望ましい環境さえ整えば子供が自ら学ぶ、というところに近づき始めている。
教育家庭新聞マルチメディア号 2025年2月3日号掲載